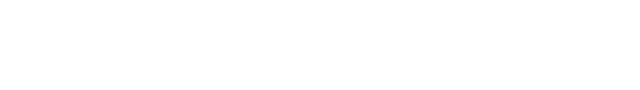自閉スペクトラム症(ASD)
症状や治療について
コミュニケーションの苦手さや、強いこだわりがある等、多様な特性がある生まれつきの発達の偏りです。下記のような困りごとになって現れます。
・空気を読むのが苦手、逆に読みすぎて疲れてしまう
・人と会話するのが苦手、複数人での話についていけない
・予定していたことが突然変わると強いストレスを感じる
・完璧主義、白黒思考(全か無か、100か0か)で折り合いをつけるのが苦手
・自分のやり方に拘りがあって他人との折り合いをつけるのが苦手
・感覚(音、光、手触り・肌触り、味、匂い)が敏感あるいは鈍感で生活上困る
・過去の嫌な記憶を何回も思い出してしまう(フラッシュバック)
スペクトラムとは「連続体」という意味であり、特性には濃淡があり、個々人の特性と環境との関係性によって生きづらさ/生きやすさが変わります。自閉スペクトラム症(ASD)の特性が極めて薄い人も含めると、かなり多くの人がその要素を持っていると考えられます。特性が濃い場合は幼少期に診断されますが、淡い場合は大人になるまで気づかれないことも多くあります。
中枢統合能力の弱さから、大局観が得にくく、局所局所を見がち(将棋やオセロなどのボードゲームで全体を見るのではなく、ある一部分に注目しがち)なため、家族や支援者からすると明確に思えるストレスと精神症状の結びつきを本人が自覚していないことが多く、そのために、心理学的な反応としての症状ではなく、「(古典的な)うつ病」や「統合失調症」と誤診されることも珍しくありません。
特性を矯正することは難しく(自由診療で短時間の一時的な効果を目的にrTMSを行っている医療機関もありますが当院では行っておりません)、環境調整(学校、職場、ライフスタイル)が重要です。
心理学的な反応(適応反応症と同様にストレスに対する反応)として、抑うつや不安、不眠、苛立ち、不登校、欠勤などの症状・行動がみられ、その人の状態を総合的に勘案して治療を考えていきます。気温や気圧の変化に敏感な方も多く、薬にも敏感で副作用が出やすい方もいらっしゃいます。