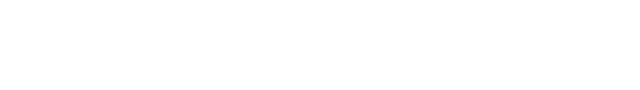不眠症
当院には、「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝の早すぎる時間に目が覚めてしまう」「ぐっすり眠れた感じがしない」といった睡眠に関するお悩みを抱えた方が多く来院されています。これらは、不眠症(ふみんしょう)の典型的な症状です。
単に「眠れない」だけでは不眠症とは診断されません。不眠によって、日中の眠気、集中力の低下、倦怠感、意欲の低下など、生活に支障が出ている場合に不眠症と診断されます。不眠症を長期間放置してしまうことで、うつ病や不安障害など他のこころの病気、精神疾患にもつながることがあります。
眠れないことでつらさを感じている方はお気軽にご相談ください。
不眠症の症状について
不眠症には以下のようなタイプがあります。
-
入眠困難
布団に入ってもなかなか寝つけず、寝付くまでだいたい1時間以上かかる(寝付けずに朝を迎えることもある) -
中途覚醒
夜中に何度も目が覚めてしまい、その頻度が10回以上に及んだり、再度寝つけない -
早朝覚醒
以前と比べて朝の早すぎる時間(例えば朝の4時など)に目が覚めてしまい、再度寝付けない -
熟眠障害
寝てはいるものの、ぐっすり眠れた感じがしない、眠った気がしない
これらの症状が1週間に数回以上、1ヶ月以上続いていて、日中の不調(日中の眠気、集中力の低下、倦怠感、意欲の低下など)がある場合、不眠症と診断されます。
不眠症の原因について
不眠の原因は一つとは限らず、いくつかの要素が重なっていることが多いです。代表的な原因を以下に挙げます。
-
ストレスや不安
仕事や人間関係のストレス、将来への不安、心配ごとがあると脳が休まらず、眠りが浅くなります。 -
生活習慣の乱れ
夜遅く、寝ようとする直前までスマートフォンやパソコンを使っていたり、昼夜逆転の生活をしていると、体内時計が乱れます。 -
身体疾患や薬の影響
疼痛や頻尿、ホルモンバランスの乱れなどにより眠りが妨げられます。服薬中のお薬の副作用として不眠が出ることもあります。 -
こころの病気、精神疾患
うつ病や双極性障害、統合失調症、不安障害、PTSD、認知症などの症状の一つとして不眠が現れることも少なくありません。
不眠症の治療法について
不眠の原因や背景は個人差があり、非薬物療法と薬物療法を組み合わせて行います。
1. 生活習慣の改善(非薬物療法)
寝室環境の整備や食習慣・運動習慣の見直し、起床・就床時間の見直し、カフェインやアルコールの摂取制限などの睡眠衛生指導に従った生活習慣の改善を行うことが勧められますが、通りいっぺんではなく、個々人の実情に沿って考えることが重要です。認知行動療法(CBT-I)が行われることもあります。
2. 薬物療法
薬物療法としては睡眠薬(睡眠導入剤)を用いることが基本ですが、睡眠改善を期待して漢方薬や抗うつ薬、抗精神病薬などを適宜使用することもあります。昔は危険な睡眠薬が多かったのですが、今は睡眠薬も進化しており、依存性や耐性の少ないお薬の選択肢が増えていますので、ご安心ください。
院長より
不眠症は、軽く見られがちですが、放っておくと大きな心身の不調に繋がることがあります。薬物療法を行う場合でも、より安全なお薬を優先して処方することを基本方針としていますのでご安心ください。
当院は西武新宿線・武蔵関駅から徒歩1分と通いやすい立地にあります。学生の方からご高齢の方まで、どんな世代の方でも気軽にお越しいただければと思います。