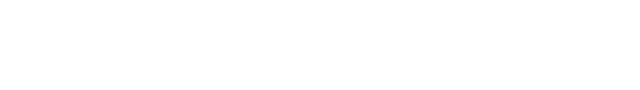強迫症(強迫性障害、強迫神経症)
症状や治療について
症状は強迫観念と強迫行為に分けて考えられます。
強迫観念は本人にとって苦痛や不安を伴うもので、それらを和らげるために強迫行為を行います。
以下に例を示しますが、強迫観念と強迫行為の種類は患者さんによって様々です。
・「お金を触ってしまった。汚いから手を洗いたい」(強迫観念)→長時間や繰り返しの過剰な手洗いやアルコール消毒をする(強迫行為)→生活に支障がある
・「ガスの元栓を閉め忘れたかもしれない。確認したい」(強迫観念)→ガスの元栓が閉まっているか何回も確認する(強迫行為)→生活に支障がある
・「家の中の物が定位置にないとモヤモヤする。整えたい」(強迫観念)→長時間かけて物の位置を整える(強迫行為)→生活に支障がある
強迫行為の結果、時間を浪費して生活への支障となることがまず問題となります。その他にも、周囲の人に強迫行為を強要したり、強迫行為に協力しないと暴力行為に及ぶなど、周囲の人を巻き込むまでに発展することもあります。
多くの場合はその不合理さを自覚していつつも強迫観念に迫られて強迫行為をやめられません。
治療にあたっては、生活のリズムを整え、過剰なストレスがあるならばそれをできるだけ少なくすることが理想的です。
まずは薬物療法で不安を和らげることが現実的で、標準的にはSSRIの定期内服を行います。薬物療法のみでは根本的な解決にならないことが多いので、暴露反応妨害法という認知行動療法を行うことが多いですが、本人の努力が求められます。
自閉スペクトラム症において苦痛の伴わないこだわりは多くみられますが、強迫症の背景に自閉スペクトラム症があることも少なくないため、多角的なアプローチが求められます。
忙しく生活していた方が、暇ができたことがきっかけで症状が悪化することも多く、ただ休息をとることが解決にならないかもしれません。
強迫症をきっかけに、うつ病になることもあるので注意が必要です。