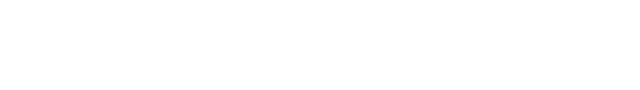うつ病
症状や治療について
下記のような、うつの症状がいくつかみられ、どういった症状が出るかは患者さんによって様々です。
・抑うつ気分(生活に支障をきたすような尋常ではない気分の落ち込み)
・興味や喜びの消失(普段楽しめていることが全く楽しめない)
・易疲労性(異常に疲れやすい)
・意欲、活動性の低下(何もやる気が起きず動けない)
・集中力や注意力・判断力・記憶力の低下、思考制止、思考抑制(脳の機能低下により簡単な思考や判断、記憶ができなくなってしまう)
・自己評価や自信の低下
・罪責感や無価値観(自分を責めてしまう、自分を無価値と思ってしまう)
・将来に対する悲観的な見方
・睡眠の異常(寝付けない、夜中に何回も起きてしまう、朝の早すぎる時間に起きてしまう、眠った感じがしない、寝過ぎてしまう、など)
・食欲の異常、体重の変化(食欲不振、過食、体重減少、体重増加)
・希死念慮(死にたいと思ってしまう)
・心気妄想(病気にかかっているに違いない、のような訂正不能な思い込み)
・貧困妄想(お金が全くない、のような訂正不能な思い込み)
・罪業妄想(重大な罪を犯してしまった、のような訂正不能な思い込み)
一言に「うつ」と言っても様々です。いわゆる古典的なうつ病とは責任感が強く、几帳面で真面目な人がなりやすい病気と言われていますが、急速に変化する現代社会においては、従来では非典型的と言われるような「うつ」が多くみられます。
双極症(双極性障害、躁うつ病)は躁状態とうつ状態を繰り返す疾患ですが、これによるうつ状態とうつ病のうつ状態は判別が難しいことも多く、家庭環境や学校・職場環境、他の併存疾患なども複雑に絡んで最終的な診断がつかないこともあります。その他にも、認知症においてその脳の変化によるうつ状態、アルコール使用障害において飲酒の影響によるうつ状態、自閉スペクトラム症や注意欠陥多動性障害においてその生きづらさによるうつ状態、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や家庭環境・学校環境等の問題によるうつ状態など、多岐に渡り、見立てや治療法は患者さんそれぞれで異なってきます。
「上司からパワハラを受けた」、「子育てが予想以上に大変」などのきっかけで、うつ病になることもあり、この状況を変えることで改善されれば、適応反応症(適応障害)と診断されることが多いですが、きっかけはあくまできっかけなので、このような場合にも抗うつ薬がよく効くことがあります。
古典的なうつ病では最も抗うつ薬の有効性が高いのですが、上にご紹介した二次的なうつ状態においても、ある程度の有効性は認められ、治療への反応性は予想外に高いことも珍しくないため、うつ状態で苦しい方は薬物療法を試みる価値は高いのです。もちろん薬への抵抗感や副作用のご心配があると思いますので、ご希望を伺いながら方針を決めていきます。